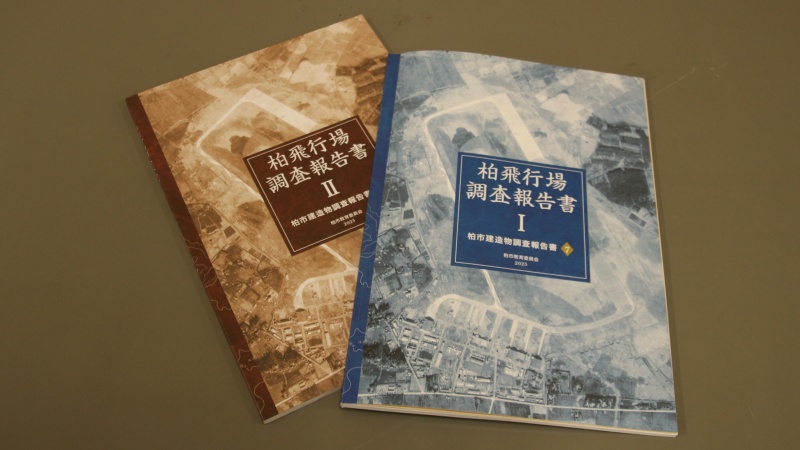
かつて「首都防衛」のために造られた陸軍柏飛行場(現・柏市)について、その建設からロケット戦闘機「秋水」の配備準備、戦後の変遷をまとめた報告書を、柏市教育委員会が上下巻でまとめ、8月8日に公表した。これまでに、市民団体や自治体が進めてきた調査の成果がまとまめられ、米軍撮影の空中写真なども多数盛り込まれた、価値ある報告書になっている。市のHPで閲覧できる。
柏飛行場は1938(昭和13)年に開設された。前年に日中戦争が始まり、東京外縁部に防空のための施設整備が進む中で、建設された。広さは東西約1500㍍、南北約1300㍍の多角形で、滑走路は1943年の資料では約1000㍍だったが、敗戦前後には約1500㍍に伸びていた。報告書は飛行場の変遷を、日本側の資料だけでなく、米軍撮影の空中写真も使いながら追い、現在のつくばエクスプレス(TX)や柏の葉公園、千葉大、東大のキャンパスに飛行場の姿を重ね合わせていく。
飛行場開設と同じころに高射砲の部隊が柏に移駐、陸軍病院や陸軍気象部観測所も整備された。さらに、日立製作所など軍需工場も次々進出してきた。報告書は「柏市域は、首都防衛のための軍事施設が多く設けられた軍郷となっていった」と指摘する。
飛行場には、教育部隊のほか、戦闘機の部隊が配置されていたが、高度1万㍍を飛ぶアメリカの爆撃機B29に対し、従来の戦闘機では歯がたたなかった。陸海軍は、ドイツで開発されたロケット戦闘機をモデルにした「秋水」の開発を44年から始め、柏飛行場は配備先の一つに決まり、燃料庫建設などが進んだ。しかし秋水は完成しないまま、日本は敗戦を迎えた。TX柏の葉キャンパス駅近くには、今も燃料庫の一部が残り、報告書は地図や写真、復元図などで当時の様子を再現する。
柏飛行場の南東約10㌔につくられた藤ケ谷飛行場(現・海上自衛隊下総航空基地)にも触れる。近年の調査で藤ケ谷飛行場の周辺でも、秋水の燃料庫跡が確認されたためで、その写真や資料も掲載された。
報告書は、市民団体の柏歴史クラブや県、市による調査が近年進み、当時の姿が明らかになってきたことから、市教委が最新成果をまとめることにした。執筆は、櫻井良樹・麗澤大教授(日本近代史)を中心に、柏歴史クラブ代表でもある上山和雄・国学院大名誉教授(同)、秋水研究家の柴田一哉さんらが担当した。
櫻井教授は「柏飛行場があったから、今の(TX沿線の)柏北部開発が可能になった。柏飛行場は、まさに今につながるものだ。報告書は、すでに失われたその姿を、今もまだ現地に残っているものや米軍資料、関係者の証言、発掘の成果、文献を踏まえ、復元することを目指した」と話す。
今後、市立図書館などに置かれ、閲覧することができるようにする予定だが、担当の市文化課のHP「建造物調査報告書」でも閲覧、ダウンロードできる。





